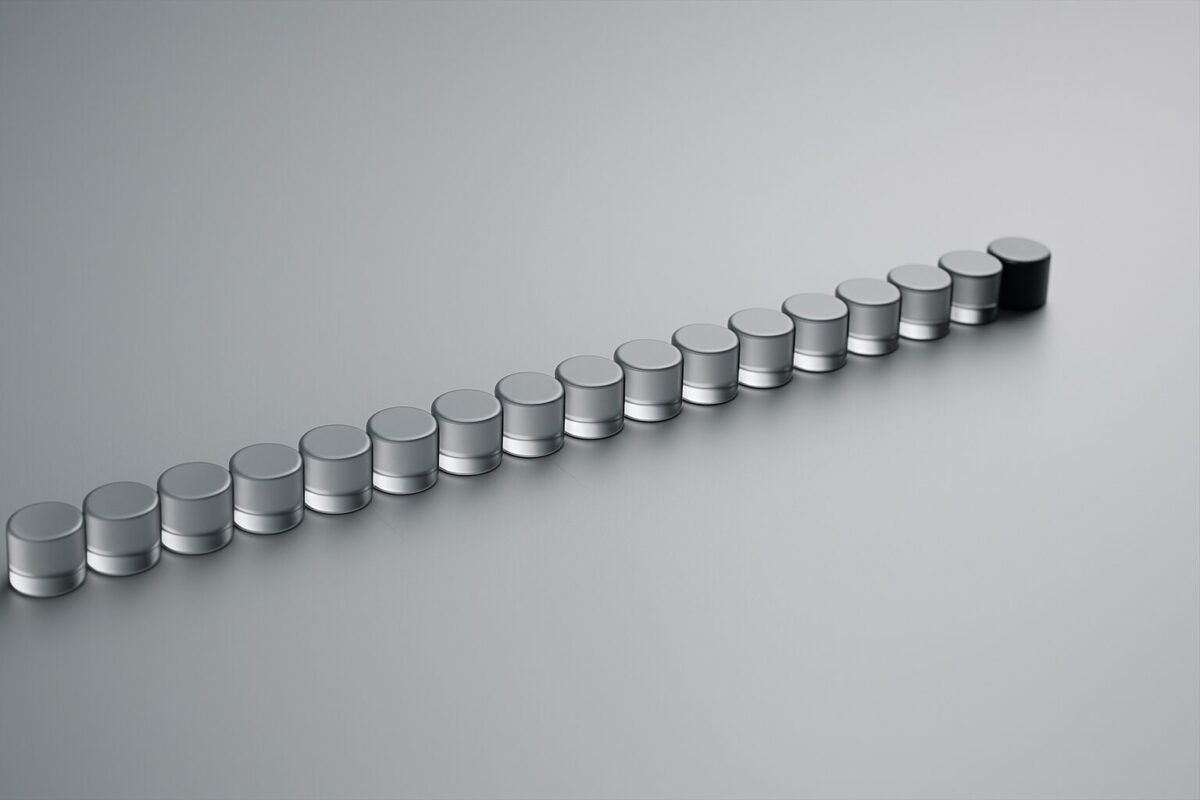「30」って言ったら負けなゲームを知っていますか?
1から順番に数字を言っていき、最終的に「30」を言った人が負けというアレです。
※一部では「カウント30」とも呼ばれているようですが、正式な名称・固定化された名称が今のところ見当たらないので、この記事ではそのまま「30って言ったら負けゲーム」と呼びます。笑
実は、このゲームを2人でやる場合、先手であれば必ず勝てる「必勝法」が存在します。
自分が後手であっても、相手がこの必勝法を知らない限りは、わりと勝てる方法だと思います。
逆にいえば、相手がこの必勝法を知っていて先手を取られてしまった場合は、(相手がミスらない限り)負け確定と言えるでしょう。
この記事では、そんな必勝法のやり方や考え方を解説します。
まずは基本的なルールをおさらい
まずは、「30って言ったら負けゲーム」の基本的なルールを確認しておきます。
基本的なルール:
- 1から順番に数字を言っていく。
- 一回に言える数字の個数は「1つ~3つまで」。
- 「パス」や「数字を言わない」は使えない。
- 「30」と言った人が負け。
つまり、「30」の所で順番が来てしまった人(「29」と言った人の次の順番の人)が負けとなります。
必勝法が使える前提条件
今回ご紹介する必勝法が通用するには、以下の前提であることが必要です。
- 先手であること。
- 参加人数は2人だけであること。
なので、ここではその前提で必勝法を解説していきます。
必勝法のやり方・考え方
それでは本題です。
まず、上記の前提(2人のみ)で行う場合、
「30」と言ったら負け=「29」と言えれば勝ち。
ということになります。
まずは、この「29」を確実に言うためにはどうすればいいか?という視点を覚えておいてください。
コントロール可能なブロック単位「4」
次に鍵となるのが、”自分がコントロール可能なブロック単位“を把握することです。
上記の前提(一回に言える数字は「1つ~3つまで」)の場合、コントロール可能な単位は「4」です。
これはどういうことかというと、「自分が数字を4つずつ固定してゲームを進められる」ということです。
例えば、
相手が「1」と言えば、自分は「2、3、4」と言う。
相手が「1、2」と言えば、自分は「3、4」と言う。
相手が「1、2、3」と言えば、自分は「4」と言う。
こだまでしょうか
つまり、相手がどの数字を言ったとしても、自分が「4」の括りで調整・支配できるということになります。
1234
1234
1234
それを踏まえ、さきほどの「29と言えれば勝ち」を思い出してみてください。
割り算の「余り」を先に言う
上記までの内容
①「29」を言えれば勝ち
②「4つ」に固定して進められる
という前提がある場合、”割り算をしてその「余り」を求める“ことで、初手でどの数字まで言えばいいかが分かります。
今回の場合、上記①÷②、つまり「29÷4」をします。(答:7、余り1)
余りは「1」ですね。
なので、初手でこの「1」を言います。
(「1」が言えれば勝ち確定)
「30」までの内訳:
そこから「30」まで具体的にどう進めるのか、実際の数字で見てみましょう。
※文字色「赤」の数字は、自分が言うべき数字です。
1…先手で自分が言う数字
<4つずつで固定して進めていく>
2、3、4、5
6、7、8、9
10、11、12、13
14、15、16、17
18、19、20、21
22、23、24、25
26、27、28、29
相手「30」(負け)
進め方の概要:
1.先手で「割り算の余りの数」を言う。(今回は29÷4の余り「1」)
2.その後、自分が上記ブロックの末尾になるよう調整しながら数字を言っていく。
(5、9、13、17、21、25、29)
例:
相手が「2」と言ったなら自分は「3、4、5」
相手が「2、3」と言ったなら自分は「4、5」
相手が「2、3、4」と言ったなら自分は「5」
…の繰り返しで進めていく。
もし自分が後手の場合、上記ブロックの末尾ポジション(5、9、13、17、21、25、29)のいずれかを、どこかのタイミングで奪う必要があります。相手が必勝法を知らなければ、このポジションを途中で奪える可能性がありますが、相手(先手)が必勝法を知っている場合はまず譲ってもらえないでしょう。
Webですぐ遊べる「30って言ったら負けゲーム」(カウント30)
必勝法パターン別解説
ここまでは基本的なパターンで解説しました。
ここからは、上記の必勝法の考え方を、他のパターンに当てはめてシミュレーションしてみます。
- パターン①:
- 「40」と言ったら負け
- 一回に言える数字は1〜3個まで
- パターン②:
- 「50」と言ったら負け
- 一回に言える数字は1〜4個まで
目標の数字や言える個数が変わると、初手で言う数字も変わります。
パターン①:「40」と言ったら負け(1〜3個まで)
基本設定:
- 「40」と言ったら負け=「39」と言えれば勝ち
- 一回に言える数字は「1つ~3つまで」
- コントロール可能なブロック単位は「4」(変わらず)
初手の計算: 39÷4=9、余り3
なので、初手でこの「1、2、3」を言います。
「40」までの内訳:
1、2、3…先手で自分が言う数字
<4つずつで固定して進めていく>
- 4、5、6、7
- 8、9、10、11
- 12、13、14、15
- 16、17、18、19
- 20、21、22、23
- 24、25、26、27
- 28、29、30、31
- 32、33、34、35
- 36、37、38、39
確保する末尾: 7、11、15、19、23、27、31、35、39
パターン②:「50」と言ったら負け(1〜4個まで)
基本設定:
- 「50」と言ったら負け=「49」と言えれば勝ち
- 一回に言える数字は「1つ~4つまで」
- コントロール可能なブロック単位は「5」(4+1)
初手の計算: 49÷5=9、余り4
なので、初手でこの「1、2、3、4」を言います。
「50」までの内訳:
1、2、3、4…先手で自分が言う数字
<5つずつで固定して進めていく>
- 5、6、7、8、9
- 10、11、12、13、14
- 15、16、17、18、19
- 20、21、22、23、24
- 25、26、27、28、29
- 30、31、32、33、34
- 35、36、37、38、39
- 40、41、42、43、44
- 45、46、47、48、49
確保する末尾: 9、14、19、24、29、34、39、44、49
Webですぐ遊べる「30って言ったら負けゲーム」(カウント30)
注意点1:余りがないパターンでは先手は不利(後手必勝)
実は、余りがないパターンでは先手は逆に不利になってしまいます。
余りがないパターン:
「41」と言ったら負け(1〜3個まで)
基本設定:
- 「41」と言ったら負け=「40」と言えれば勝ち
- 一回に言える数字は「1つ~3つまで」
- コントロール可能なブロック単位は「4」
初手の計算: 40÷4=10、余り0
余りが0の場合 → 先手必敗パターン
余りがないということは、目標の数字「40」がブロック単位「4」でちょうど割り切れるということです。
この場合、後手が必勝法を使えるようになります。
後手の戦略: 先手が何を言っても、後手が「4の倍数」を確保し続ければ勝てます。
- 先手が「1」→後手が「2、3、4」
- 先手が「1、2」→後手が「3、4」
- 先手が「1、2、3」→後手が「4」
後手が確保する末尾: 4、8、12、16、20、24、28、32、36、40
つまり、余りが0の場合は「後手有利」となり、先手に確実な必勝法はありません。 先手としては、相手がこの必勝法を知らないことを祈るか、相手のミスを誘うしかないということですね。
注意点2:勘の良い人は勝ちパターンに気付く
絶対に勝てるからと言って、あまりにも得意げに何回もやっていると、勘の良い人は気付いてしまう場合があります。笑
勘の良い人:
あれ?コイツ毎回25って言ってないか?よく聞くと21も毎回言ってるな、その前は…その前は…そして最初は1でとどめてるのか。はっはーんなるほど(ニヤリ
といった感じで、必勝法を知らなくとも逆算して勝ちパターンを理解していく人が居るので、ほどほどに。
“必勝法を知っている人”を見分けるポイント
今回説明した必勝法は、(余りがないパターンを除いて)まさに「先手必勝」の方法です。
そのため、両者が必勝法を知っているケースでは順番決め(じゃんけんの勝ち負けなど)がゲームの勝敗に直結してしまいます。
なるべく勝ちたいなら、そもそも”必勝法を知っている人との勝負は避ける”のも、勝率を上げるための一つの手ですね。笑
そこで、“必勝法を知っている人”を見分けるためのポイントも記しておきます。
必ず当てはまるというわけではないので、あくまでも参考程度で。
3人以上でのゲームを提案し、反応を見る
今回の必勝法は、ゲームを3人以上でやる場合は使えません。「4ごとの単位」でコントロールできないうえに、先手になれるかすら怪しいからです。
なので、3人以上でのゲームを提案し、相手が焦るかどうかを見てみてください。焦ったり躊躇するそぶりがある場合、もしかすると「必勝法が使えなくなるから」そうなっているのかもしれません。
「30」ではなく他の(大きめの)数字を設定してみる
ゲームの設定値を「30」ではなく「40」や「50」にして勝負してみるのも、一つの見極めポイントです。
- 設定「30」の時より考える時間が長い。
- ブロック単位の末尾を綺麗に言い当ててくる。
相手にこれらの傾向がみられる場合、もしかすると頭の中で必勝法を計算しているのかもしれません。
Webですぐ遊べる「30って言ったら負けゲーム」(カウント30)
おまけ:ちょっと数学ちっくな話
この記事で説明している「ブロック単位での考え方」は、数学的には「剰余演算(じょうよえんざん)」または「モジュロ演算」と呼ばれるものです。
※剰余演算・モジュロ演算:割り算の余りを求める演算のこと。ある数値を別の数値で除算(割り算)し、余りを取得する。
記事では「29÷4の余りを求める」という計算をしていますが、これがまさに剰余演算です。数学記号では「29 mod 4 = 1」と書きます。
また、より広い概念としては「合同式(ごうどうしき)」や「剰余類(じょうよるい)」という考え方もあります。「4つずつのブロック」で数を分類していくのは、まさに「mod 4」での剰余類に分けているということになります。
ちなみに、ゲーム理論の文脈では、このような必勝法を見つける手法は「後退解析(backward induction)」とも関連しています。
後退解析(backward induction)とは…
ゴールから逆算して最適な戦略を導く思考法。
「最終局面で何が起こるか」→「その1つ前では何をすべきか」→「さらにその前では…」と、終わりから遡って考えることで、各段階での最善手を決定します。
ゲーム理論や動的計画法で用いられる基本的な解法で、「30って言ったら負けゲーム」のように有限回で終わるゲームの必勝法を見つけるのに有効です。
横並びの間違い探しを瞬時に解く裏技【平行法ですぐ見つけるコツとは】
まとめ
「30って言ったら負けゲーム」の必勝法は、以下の3つのポイントで成り立っています。
必勝法の核心:
- 目標−1を言えれば勝ち(30なら29、40なら39)
- ブロック単位でコントロール(言える個数+1が基本単位)
- 余りを初手で言う((目標−1)÷ブロック単位)
先手・後手の有利不利:
- 余りがある場合 → 先手必勝
- 余りが0の場合 → 後手必勝
実践のコツ:
- 両者が必勝法を知っている場合、勝負は「じゃんけん」で決まる
- 相手に必勝法がバレないよう、ほどほどに
- 3人以上では必勝法が使えないので注意
このゲームは一見単純ですが、実は数学的な論理が隠れている奥深いゲームです。 ぜひ友達や家族と試してみてください!