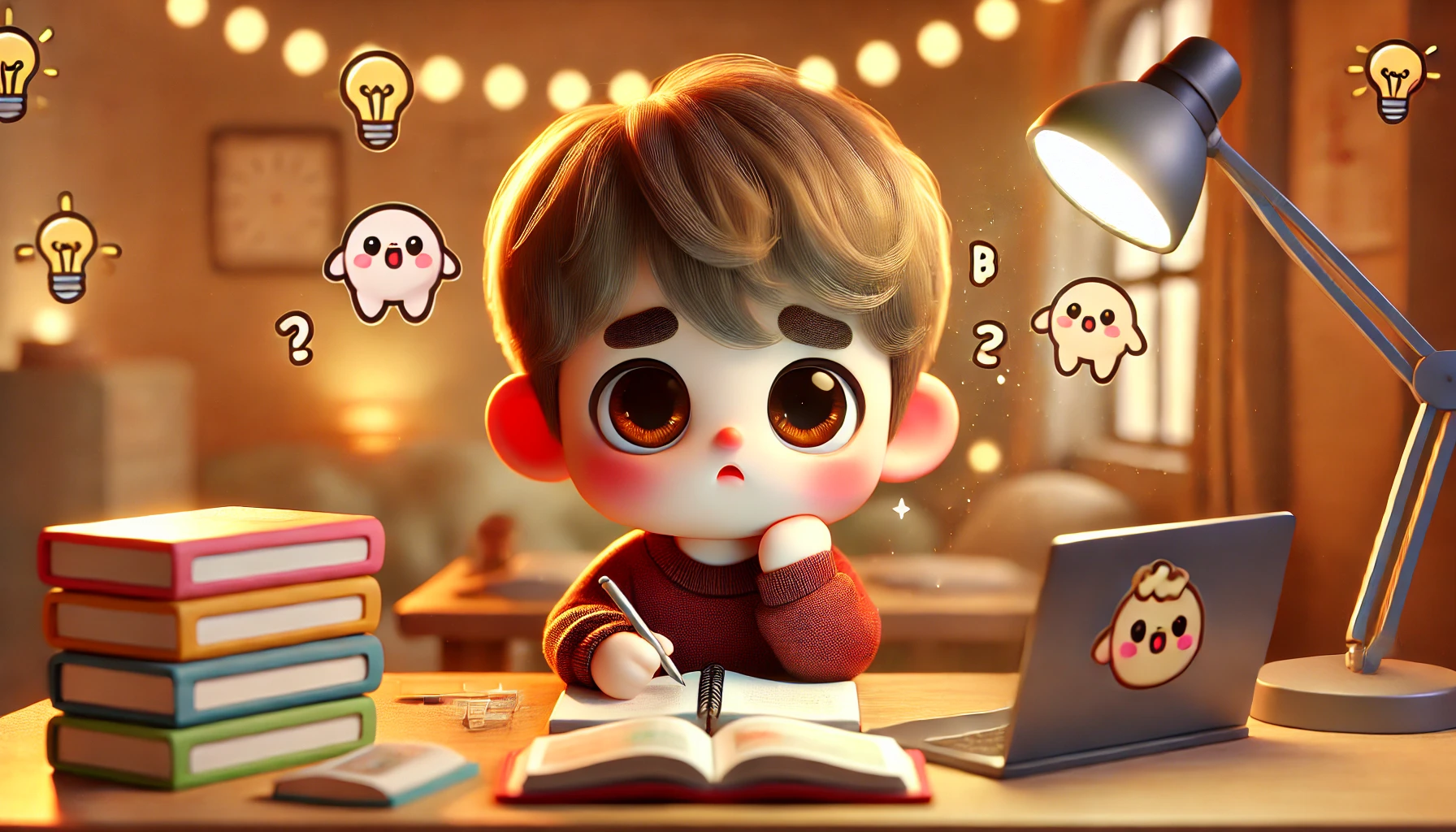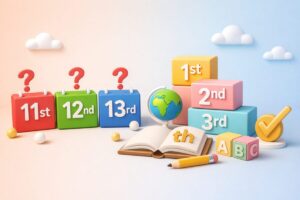中学生になると、勉強の難易度が上がり、生活リズムも変わるため「成績が急に下がった…」と悩むケースが増えます。この記事では、成績が下がる主な原因を解説し、中学1年・2年・3年それぞれの対策を紹介。さらに、学習習慣の改善方法や保護者によるサポート方法も詳しく解説します!
目次
中学生の成績が急降下する主な理由
学習内容の難易度が一気に上がる
- ポイント
中学校では英語や数学・理科で文法、方程式、関数など、抽象度・応用度が高い領域に進むため、理解が追いつかないと成績が下がりやすいです。 - 個人差の補足
小学校から学習塾に通って先取り学習をしていた生徒は、ギャップを感じにくい場合もあり、一律ではありません。 - データ面(例示)
- 文部科学省の「全国学力・学習状況調査」では、中学3年生の英語の平均正答率が低く、特に「話すこと」の領域で課題があることが報告されています。
参考:令和 5 年度全国学力・学習状況調査(PDF) - 東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所の共同研究「子どもの生活と学びに関する親子調査2022」では、中学生の68.1%が「上手な勉強のしかたがわからない」と回答しており、年々増加傾向にあります。
参考:「上手な勉強のしかたがわからない」という悩みが約 7 割に増加(PDF)
- 文部科学省の「全国学力・学習状況調査」では、中学3年生の英語の平均正答率が低く、特に「話すこと」の領域で課題があることが報告されています。
生活リズムの変化(部活動・SNS・家庭環境など)
- ポイント
部活動や学校行事で帰宅が遅くなると勉強時間の確保が難しくなるのは一般的ですが、近年はSNSや動画サイトによる夜更かし・睡眠不足も無視できない要因になっています。 - 家庭やSNSの影響
- 家庭内での役割(きょうだいの世話、家事の手伝いなど)に追われる
- スマホの長時間利用、SNS通知による集中力の削がれ
- 家庭環境の不安定さ(親子関係のトラブル等)
- データ面(例示)
- 「スマホやSNSの利用時間が1日3時間以上の生徒は、学力が平均未満になる傾向がある」との調査結果があります。
参考:研究者が思わずゾッとした「子どものスマホ使用時間と偏差値の関係」小中学生7万人調査でわかった衝撃の事実 - 部活動に未加入の生徒でも、SNSの長時間利用や家庭内の事情により、勉強時間が確保しづらいケースが報告されています。
参考:SNS使用時間が増えると正答率が低下傾向 学力調査、文科省は警鐘
- 「スマホやSNSの利用時間が1日3時間以上の生徒は、学力が平均未満になる傾向がある」との調査結果があります。
思春期特有の心理的変化(自我の揺れ・家庭環境の影響)
- ポイント
思春期には自己肯定感や自尊感情が大きく揺れ動き、友人関係・進路不安・家庭内の問題など多方面のストレスが学習意欲や集中力を損なう原因になることがあります。 - 科学的裏付け
文部科学省の調査でも、自己肯定感と学力には一定の相関があると指摘されています。また、ベネッセ教育総合研究所の調査でも、自己効力感と学力の関連性が報告されています。
参考:令和 5 年度全国学力・学習状況調査(PDF)
勉強方法が合っていない/わからない
- ポイント
中学では「自学自習」の比重が大きくなるため、自分に合った勉強法を確立できないと急激に成績が落ちることがあります。 - 具体例
- 書いて覚える → ノートまとめ型
- 音読が効果的 → リスニング・発話重視型
- 図やグラフで視覚化 → ビジュアル型
- 誰かに説明して覚える → グループ学習型
- デジタルツール・アプリ活用 → オンライン型
- 学習スタイル診断チェック(例)
下記のように自分に当てはまる項目が多いタイプを把握し、勉強法を工夫すると良いでしょう。
学習スタイル診断チェック(例)
□ 書いて覚えるのが得意 … ノートまとめ型
□ 音読やリスニングで理解が深まる … リスニング学習型
□ 図や色分けがあると整理しやすい … 視覚学習型
□ 友人や家族に説明すると理解が進む … グループ学習型
□ スマホやタブレットの学習アプリで勉強している … オンライン学習型
学年別に見る「急降下の時期」と効果的な対策
中学1年生(中1)
急降下しやすい時期
- 中学入学直後~夏休み前後
主な理由
- 小学校との差(学習難度・授業スピード)
- 新生活への適応(部活動やSNSなど新しい刺激が多い)
効果的な対策
- 学習習慣の早期確立
- 1日15~30分でも机に向かう「ルーティンタイム」を設定
- 短い時間でも復習と予習を欠かさない
- 基礎固めの徹底
- 英単語や基本計算など、基礎が後々まで影響する教科を優先
- 「わからない」箇所を翌日までに必ず解消
- 生活リズムとスマホ利用の管理
- スマホの利用時間を親子でルール化(夜○時以降は使わない など)
- SNSや動画視聴は適度に制限し、集中できる時間帯を作る
中学2年生(中2)
急降下しやすい時期
- 中2の夏休み前後
- 「中だるみ」しやすい時期
主な理由
- 学習内容がさらに難化(英数で応用力が問われる)
- 部活動やリーダー的役割の負担増
- 思春期の悩みやSNSトラブルが本格化
効果的な対策
- 計画的な学習スケジュール
- テスト前だけでなく普段から週単位・月単位で学習計画を立てる
- 学習範囲を細分化し、達成感を得やすくする
- 部活動・SNSとの両立工夫
- 通学時間・部活の待ち時間など、隙間学習を有効に活用
- SNS・動画アプリの通知をオフにして、勉強モードを確保
- ストレスケアと自己肯定感の維持
- 友人・家族・教師との相談の機会を増やす
- 気分転換(軽い運動や趣味)を取り入れ、精神的疲労を溜め込みすぎない
中学3年生(中3)
急降下しやすい時期
- 中3の夏休み明け~受験期
主な理由
- 受験勉強 + 定期テスト + 内申点対策で学習量が急増
- 志望校・将来への不安やプレッシャー
- 秋以降の疲労蓄積によるモチベーション低下
効果的な対策
- 長期的学習計画と内申点対策
- 志望校の出題傾向と内申点対策を同時に考える
- 日々の授業・提出物・定期テストをおろそかにしない
- 過去問・模試の活用
- 定期的に模試や過去問に取り組み、弱点分野を明確化
- 解き直しを丁寧に行い、学習効率を高める
- プレッシャーへの対処法(メンタルケア)
- 目標をスモールステップで設定する
例:「模試で偏差値○○を取る!」ではなく、「今週はこの単元をマスターする」「この問題集を1日5ページ進める」といった、達成しやすい小さな目標を立てる。 - 進捗を記録し、成長を実感できる工夫
例:「できるようになったことリスト」を作る(英単語50個を覚えた、数学の連立方程式が解けるようになった、など)。これにより、自信をつけながら受験対策を進められる。 - 4-7-8呼吸法(4秒吸う → 7秒止める → 8秒かけて吐く)でリラックス
- 勉強の合間にストレッチや軽い運動をして気持ちを切り替える
- 「受験はあくまで将来への通過点」と捉える(認知行動療法的なアプローチ)
例:「合格=成功、失敗=ダメではなく、『受験勉強を通して努力する力がついた』と考えるようにする」
- 目標をスモールステップで設定する
学年を問わず有効な「学習習慣づくり」のポイント
- 自分の学習スタイルを知る
- 前述の「学習スタイル診断チェック」などを参考に、多様な学習方法を試してみる
- 書く、音読する、グラフ化する、デジタルを使う…など、自分に合った方法を組み合わせる
- 学習記録・振り返りの徹底
- 毎日の学習時間や内容・理解度を簡単にメモし、客観的に進度を把握
- 成績が下がった・上がった原因を分析し、次の計画に活かす
- 家庭・学校・塾などの連携
- 必要に応じて塾やオンライン教材も活用し、苦手分野を補強
- 学校の先生への質問や、保護者とのコミュニケーションで早期に悩みを解消
- 生活リズム・メンタルヘルスの管理
- 十分な睡眠時間の確保(スマホ利用をコントロールし、夜更かしを防ぐ)
- ストレスが高まったときは軽い運動や趣味で気分転換を図る
親の関わり方:具体例
- 「会話の促し」
- 子どもと一緒に学習計画を立てる
例:「1週間の勉強スケジュールを一緒に作る」「何をどの時間にやるか相談して決める」など、親が「計画づくりのサポーター」になる。 - 学習記録の振り返りを一緒にする
例:「1週間後に『計画どおり進められた?』『どこが難しかった?』と振り返る機会を設ける」ことで、次の学習計画に活かせる。 - 「褒める」ポイントを増やす
例:「今日、30分間ちゃんと集中して勉強できたね!」と、結果ではなくプロセスを重視した声かけを心がける。
- 子どもと一緒に学習計画を立てる
- 「環境づくり」
- リビング学習が合う子には集中しやすいスペースを作り、適度に声掛けをする。
- 一人でじっくりやりたいタイプなら、静かに取り組める机と道具の配置を整える。
- 「学習スタイルの合意形成」
- 子ども自身が「自分に合った勉強方法」を見つけられるよう、塾や家庭教師、オンライン教材を試してみることを一緒に検討する。
- ルールは押し付けではなく、子どもと話し合ったうえで決め、定期的に見直す。
まとめ
中学生の成績が急降下する要因には、学習内容の難化、生活リズムの変化(SNSや家庭環境の影響も含む)、思春期特有の心理的揺らぎ、自分に合わない勉強法など、複数の要素が密接に絡み合っています。さらに近年では、スマホやSNSの利用時間の増加も学習時間を圧迫する要因になっています。
しかし、以下のように学年ごとの特徴をおさえた対策と、適切な学習方法の選択、家族や学校との連携を組み合わせることで、成績の急降下は防ぐことが可能です。
- 中1:学習習慣を早期に確立し、基礎固めを徹底する
- 中2:中だるみを防ぎ、計画的な学習とストレスケアでモチベーションを維持
- 中3:入試を見据え、内申点と受験勉強の両立を図りつつ、プレッシャーをコントロール
さらに、「自分に合った勉強スタイルの確立」「家庭・学校・塾の連携」「メンタルヘルス管理」を意識して進めることで、継続的な学力向上が期待できます。保護者は「勉強しなさい」という指示ではなく、日々の努力や工夫、勉強以外の面でも励ましやポジティブな声掛けを行うことで、子どもが安心して学べる環境を整えてあげましょう。