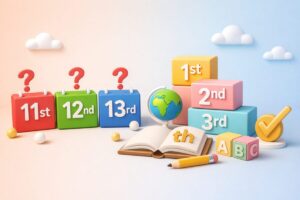「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」
私たちに馴染み深い十二支ですが、この中に「猫」がいないことを不思議に思ったことはありませんか?実は、十二支に猫がいない理由は、「ネズミに騙されたから」という有名な昔話が最もよく知られています。
しかし、歴史をたどると、もっと現実的な理由も見えてくるのです。
この記事では、子供から大人まで楽しめる十二支と猫の物語から、その背景にある歴史的な真実、さらには猫が十二支に入っている国の話まで、分かりやすく解説していきます。
十二支に猫がいない最も有名な理由|ネズミの策略だった?
なぜ十二支に猫がいないのか、その理由として最も有名なのが、ネズミに騙されてしまったという、ちょっぴり切ない昔話です。一度は耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
物語は、ある年の暮れ、神様が動物たちに出した「お触れ」から始まります。
「元旦の朝、私のところに挨拶に来た者から順に、12番目までをその年の大将としよう」
これを知った動物たちは、我こそが一番乗りだと意気込みました。猫ももちろん、その一人(一匹)です。しかし、猫はうっかり神様のもとへ行く日を忘れてしまい、友達のネズミに尋ねました。
するとネズミは、本当は元旦だと知っていながら、わざと「1月2日だよ」と嘘の日付を教えたのです。
すっかり信じ込んだ猫は、翌日(元旦)の朝は家でゆっくりと過ごし、次の日に神様のもとへ向かいました。しかし、そこではすでに12匹の動物たちが大将として決まった後で、祝賀会が行われていました。
自分が騙されたことに気づいた猫は、激怒してネズミを追いかけます。この物語が、今でも猫がネズミを追いかける理由になった、と言われているのです。なんとも猫が可哀想になるお話ですね。
本当の理由は?十二支が成立した時代背景
「ネズミの裏切り伝説」は非常に有名ですが、実は学術的にはもっと有力な説があります。それは、十二支が誕生した頃の中国で、イエネコがまだ人々に広く知られていなかった、というものです。
十二支の原型は、今から3000年以上前の古代中国(殷の時代)にさかのぼります。しかし、現在のように動物と結びつけられたのは、戦国時代から漢の時代(紀元前3世紀〜紀元前2世紀頃)にかけてとされています。当時、人々が暦を覚えやすいように、身近な動物を割り当てていったのが始まりです。
選ばれた動物たちを見ると、牛や馬、羊、鶏、豚(日本では猪)など、当時の人々の生活に欠かせない家畜が中心です。
では、肝心の猫はどうだったのでしょうか。もちろん、古代中国にも野生のヤマネコ類は生息していました。しかし、現在のような「イエネコ(家猫)」が本格的に中国に伝わり、人々の間で広く飼われるようになったのは、十二支が定着した後の漢の時代以降だと考えられています。つまり、動物のメンバーを決める際に、イエネコはまだ人々の暮らしに身近な存在ではなかったのです。
物語としては少し味気ないかもしれませんが、こちらが最も有力な「本当の理由」とされています。
【国によって違う】猫が十二支に入っている国もある!
日本では十二支に猫がいませんが、世界に目を向けると、なんと猫が十二支のメンバーになっている国が存在します。文化や環境が違えば、十二支の動物も少しずつ変わるのが面白いところです。
特に有名なのがベトナムです。ベトナムの十二支は、日本の「卯(うさぎ)」の代わりに「猫」が入っています。
| 日本の十二支 | ベトナムの十二支 |
|---|---|
| 子(ねずみ) | 子(ねずみ) |
| 丑(うし) | 丑(水牛) |
| 寅(とら) | 寅(とら) |
| 卯(うさぎ) | 卯(ねこ) |
| 辰(たつ) | 辰(たつ) |
| 巳(へび) | 巳(へび) |
| 午(うま) | 午(うま) |
| 未(ひつじ) | 未(やぎ) |
| 申(さる) | 申(さる) |
| 酉(とり) | 酉(にわとり) |
| 戌(いぬ) | 戌(いぬ) |
| 亥(いのしし) | 亥(ぶた) |
なぜベトナムではウサギではなく猫なのでしょうか。これにはいくつかの説がありますが、有力な説の一つとして、中国語の「卯(mǎo)」の発音が、ベトナム語の「猫(mèo)」と似ていたために置き換わった、というものが挙げられます。また、ベトナムの気候や文化において、ウサギよりも猫の方がより身近な動物だったことも理由の一つと考えられます。
このように、十二支の動物は、国や地域によって少しずつ異なっているのです。
猫以外にもいる?十二支に選ばれなかった動物たち
十二支の動物は、神様のもとへ駆けつけた順番で決まった、という昔話があります。では、猫以外に選ばれなかった動物たちはどうしていたのでしょうか。また、なぜキツネやタヌキ、あるいはライオンやゾウのような強そうな動物が選ばれなかったのか、気になりませんか。
これには、先ほども触れた「当時の人々の生活との関わり」が大きく影響しています。十二支に選ばれた動物は、ネズミを除くと、その多くが家畜や、農耕・牧畜において重要な役割を果たしてきた動物たちです。
例えば、牛は農作業を手伝い、馬は人や物を運び、羊は毛や肉を提供してくれます。鶏は時を知らせ、犬は家を守り、猪(豚)は貴重な食料でした。
一方で、キツネやタヌキのような動物は、地域や時代によっては人里に現れて作物を荒らすなど、家畜とは少し違う存在と見なされていました。ライオンやゾウのような動物は、当時の中国において、人々の生活圏にはいなかったため、候補にはならなかったようです。
つまり、十二支の選定基準は、足の速さや力の強さではなく、「いかに人々の暮らしに密着し、役立ってきたか」という点が重要だったと考えられます。そう考えると、十二支のラインナップにも納得がいきますね。
幸運を呼ぶ猫の名前30選!和風から海外風まで意味を込めて紹介
まとめ:十二支と猫の物語が今も愛される理由
今回は、十二支に猫がいない理由について、有名な昔話から歴史的な背景までを掘り下げてきました。
- 有名な昔話: ネズミに騙されて元旦の集まりに行けなかったから。
- 歴史的な理由: 十二支が成立した古代中国で、イエネコがまだ広く普及していなかったから。
史実としては「中国に広く普及していなかった説」が有力ですが、それでも「ネズミの裏切り伝説」が今なお多くの人に語り継がれているのは、その物語が持つ魅力や教訓があるからでしょう。少しおっちょこちょいな猫と、ずる賢いネズミのキャラクターは、私たち人間社会の縮図のようにも見えます。
十二支には入れませんでしたが、猫は時代を超えて世界中の人々に愛され続ける特別な存在です。もしかしたら猫自身は、十二支の座なんて気にせず、今日もどこかでのんびり日向ぼっこをしているかもしれませんね。