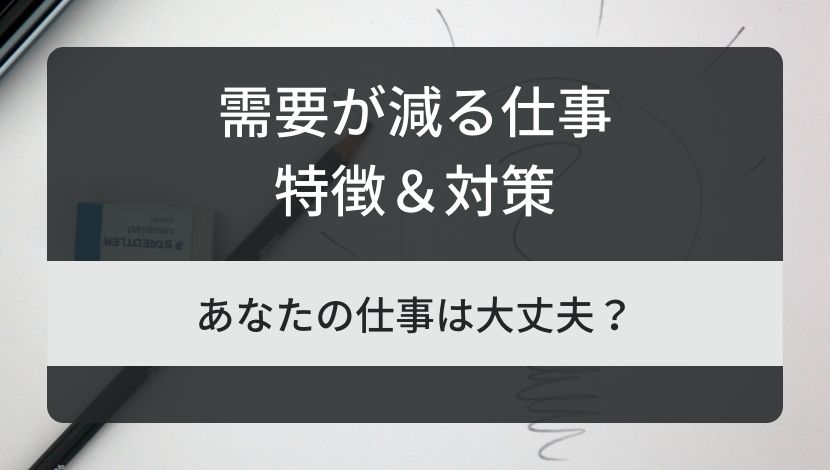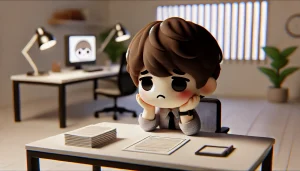AI時代を乗り越える!これから需要が減るかもしれない仕事の特徴と「失業しないための対策」
「AIや機械がどんどん進歩しているけれど、私の仕事は大丈夫なのだろうか……」
そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。実際、テクノロジーの進歩によって消えてしまった職種もあれば、新たに生まれた職種もあります。
この記事では、これから需要が減る可能性が高いと考えられる仕事の特徴を整理し、そうした仕事に従事している場合にどのように備えれば良いのかを解説します。時代の変化にしなやかに対応し、キャリアを守るためのヒントとしてお役立てください。
参考情報
たとえば、世界経済フォーラムが公表している「The Future of Jobs Report」などの分析によると、将来的に大幅な自動化が進む一方で、新しい職種やスキルの需要も増えていくと予想されています。つまり、一部の仕事は減るかもしれませんが、新たなチャンスが生まれる業界も多いのです。
需要が減る仕事の主な特徴

電子化されやすい仕事
テクノロジーの進歩により「電子化」や「オンライン化」が加速し、紙やフィルムなどアナログ媒体を扱う分野が縮小する傾向にあります。
- 出版や新聞など紙媒体を扱う業界
電子書籍、オンラインニュース、SNSなどの普及が続き、紙を中心としたビジネスモデルは相対的に縮小しています。 - 写真現像・プリントサービス
スマートフォンやデジタルカメラの普及に伴い、街の写真現像専門店を見かける機会は大幅に減りました。ただし、証明写真や記念写真のプリントなど、特定の需要は根強く残っているため、まったくのゼロにはなりにくい部分もあります。
こうした分野で生き残るためには、「アナログだからこそ楽しめる体験」をどのように提供するかが重要です。電子化では代替できない付加価値や限定サービスなどを打ち出すことで、ニッチな需要を獲得できます。
AIや機械に代替されやすい仕事
AIやロボット技術の進歩によって「人間でなくても成立する仕事」が置き換えられる可能性が高まっています。特に定型的な業務や習慣化された業務プロセスは、AIや機械に任せたほうが効率的というケースが増えています。
- 保険の営業職
生命保険・自動車保険などのプランをネット上のAI診断で提案・見積・加入できるサービスが普及し、人員の削減傾向が見られます。ただし、じっくりと対面相談したい顧客層も一定数おり、人間ならではのサポートが付加価値になる部分は依然として残ります。 - 銀行員
フィンテックの普及やオンライン決済の増加によって、窓口業務や振込処理といった定型的業務は縮小しています。しかし複雑な投資アドバイスや企業向けの財務コンサルなどは、まだまだ専門家の知識や経験が必要です。 - 運転手・配達員
自動運転技術やドローン配送の実証実験が進んでおり、将来的にはタクシー運転手や宅配員の需要が減るかもしれません。とはいえ、法規制や技術面の課題はまだ多く、特に地方や高齢化地域では人手が欠かせないケースも当面続くと考えられます。今すぐ一斉に代替されるわけではない点を理解しておきましょう。
単純作業が中心の仕事
「単純作業」はAIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)に置き換えられやすいといわれています。マニュアル通りに同じことを繰り返すだけの仕事は、自動化によるコスト削減が望めるため、企業としても導入メリットが大きいのです。
- データ入力
スキャニングやOCR(文字認識)の精度向上により、人手を介さずに情報を電子化できるようになりました。ただし、極めて機密度の高い情報や不規則なフォーマットを扱う場合は、まだ人間の目による確認が必要とされるケースもあります。 - 工場ライン作業
組み立てや検品などパターン化された工程は、ロボットアームや自動化設備によって効率化が進みます。とはいえ、高度な職人技が必要な製造プロセスなど、一筋縄ではいかない工程は依然として人間が担う部分が残りやすいです。
ワンポイント
「需要が減る仕事」についてあまりにも一括りに考えると、例外を見落とすリスクがあります。業界や地域、企業の方針などによって変化のスピードは異なります。
需要が減る仕事に就いている場合の対策
では、現在こうした「需要が減るかもしれない仕事」に携わっている場合、どのように備えればいいのでしょうか。以下に代表的な3つの方法をご紹介します。
軸ずらし転職で段階的にキャリアチェンジ
いきなり全く未経験の領域に飛び込むのはリスクが高いです。そこで有効なのが、「軸ずらし転職」という考え方です。
- 軸ずらし転職とは?
現在の「業種」または「職種」のどちらかに軸を置きつつ、もう片方をずらして新しい領域に挑戦するキャリア戦略です。- 例)同じ業種の中で、職種を変える。
- 例)同じ職種のまま、業種を変える。
こうした段階的シフトなら、これまでの経験を活かしながら新しいスキルを身につけられるため、転職の成功率を高めやすくなります。
詳しくは以下の動画をご覧ください。
年収を上げる“軸ずらし転職”の考え方
年収アップの基本戦略「軸ずらし転職」について解説
AIを味方につけられる仕事を選ぶ
AI化が進むほど、AIを活用する仕事やAI関連のサポート業務は拡大していきます。「AIエンジニア」「AIプランナー」「データアナリスト」のような職種だけではなく、AIを導入しようとする企業へのコンサルティングや運用サポートも増えていくでしょう。
- AI×自分の専門分野
たとえば、教育現場でのAI教材活用サポートや、医療現場での画像診断支援システム運用など、「AI×○○(自分の専門や興味)」という組み合わせに着目すると新たなキャリアが開ける可能性があります。
なぜAIの影響範囲は広いのか?
AIは「大量のデータを高速で解析し、学習・パターン認識する」能力が高いため、製造・金融・医療・サービス業など業界を問わず導入が進む点が特徴です。コンピュータやインターネットを基盤にどの産業にも活用しやすいことから、「汎用技術」として多方面に影響が及んでいます。
スキルアップと職業訓練の活用
歴史を見ても、「新たな技術やツールを使いこなす人材」は常に需要が高いです。AI時代も例外ではなく、時代に即したスキルを早めに習得することが重要です。
- オンライン学習やスクール
プログラミングやデータ分析などを初心者から学べるスクールやオンライン講座が多数存在します。自分でペースを調整しながら学習できる点もメリットです。 - 公的な職業訓練制度
自治体やハローワークが主催する職業訓練では、未経験分野でも基礎から学べる講座や就職支援が用意されていることがあります。転職や再就職を考える場合、一度確認してみましょう。
時代に合わせたスキルを身につける重要性
「ラッダイト運動」という言葉をご存じでしょうか。19世紀初頭、機械化が進むイギリスの織物工場で失業を恐れた労働者が機械破壊活動を起こした運動です。しかし長い目で見ると、機械を導入することで効率化が進み、新しい雇用や産業が生まれました。
- 狩猟時代:槍や弓の扱いが生活を左右
- 農耕時代:農具や灌漑(かんがい)技術が生産力を左右
- 工業時代:機械を扱うスキルが大量生産を支える
- 情報時代:PCやスマホなどの情報機器を使いこなす力が必要
- AI時代:AIを「どう活用するか」が新たな競争力に
変化を拒むのではなく、「今の仕事+AI」「これまでの経験+新技術」を掛け合わせることで、新たな強みを持つ人材になれるはずです。汎用性が高いAI技術は、あらゆる業界に浸透しやすいからこそ、影響範囲が非常に広いのです。
これから需要が増える仕事を見据えた総合ガイド【将来性のある業界や職種とは?】
まとめ:臨機応変に行動し、新たなチャンスをつかもう
- 需要が減る傾向のある仕事の共通点
- 紙やフィルムなど、アナログ媒体が主力
- ルーティンワークや定型業務が中心
- AIや機械が代替しやすい構造
- 失業を回避するための基本戦略
- 軸ずらし転職で段階的にキャリアを広げる
- AIを味方にできる仕事や領域を学ぶ
- 継続的なスキルアップと職業訓練制度の活用
| 需要が減る仕事 | AI活用で伸びる仕事 |
|---|---|
| 出版・新聞(紙媒体) | AIエンジニア |
| 写真現像・プリントサービス | データアナリスト |
| 保険の営業職 | AIプランナー |
| 銀行の窓口業務 | AI導入コンサルタント |
| 運転手・配達員 | 医療×AI支援職 |
| データ入力 | 教育×AI活用支援 |
| 工場の単純ライン作業 | 製造現場の自動化オペレーター |
テクノロジーの進歩が速い時代だからこそ、視野を広げて柔軟に行動することが重要です。「自分の仕事がAIに代替されるかもしれない」と感じたら、スキル習得や転職活動を早めに検討してみましょう。必要に応じて公的機関の支援や転職エージェントを活用するのも一手です。
今後、すべての仕事が一気にAIに置き換わるわけではありませんが、着実に少しずつ変化の波は訪れています。先手を打って学びや準備を進め、AI時代でも活躍できるキャリアを築いていきましょう。
もしもの時には、職業訓練を受けるという選択肢もあります。誰でも新しい技術を学び直せるチャンスは多方面に存在します。臨機応変に動き、むしろこの時代の変化をチャンスと捉えて前向きに進んでいきましょう。